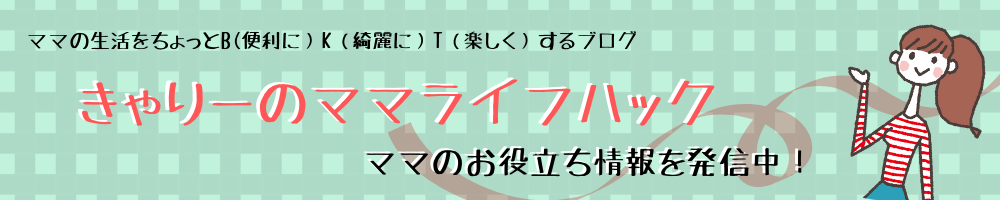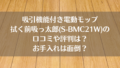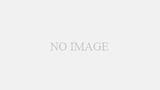最近よく耳にする宿題不要論。
宿題は、成績の向上には繋がらず、むしろ子どもの学習に対するやる気を低下させてしまうのでは?という考え方が広がっています。
確かに、子どもにとっても親にとっても先生にとっても負担になっているという声が多いのも事実です。
そこで今回は、宿題は本当にいらないのか、メリットとデメリットをご紹介します!
また、効果が出にくい宿題についても合わせてご紹介するので、ぜひ最後までお読みください♪
宿題のメリット

負担が大きく、悪者にされがちな宿題。

ですが、実はきちんとメリットもあるようです。
授業の内容を復習できる
授業で学んだ内容を家で繰り返すことで、効率よく学習内容を定着させることができます。
また、授業中には理解できなかった内容も家でじっくり考えることで理解できるようになることも。
学校ではなかなか時間が取れない音読や計算練習も、宿題なら家で時間をかけて練習することができます。
学習の習慣が身に付く
学校で学んだことを確実に定着させるためには、家庭での学習は必要不可欠です。
学校から、家庭で取り組む学習内容を宿題として出すことで、子どもたちは家での学習に取り組みやすくなります。
学校で課せられた宿題に毎日取り組むことで、「勉強するのは当たり前」という環境を作ることができます。
子どもの学習内容を親が知ることができる
宿題は、学校で学習した内容の復習が多いです。
ですから、保護者は子どもが学校でどんなことを学習しているか知ることができます。
普段、学校での授業の様子を見ることのない親にとって宿題は子どもの学習内容を知る一つの手段になります。
宿題のデメリット

一方で、宿題のデメリットも少なくありません。

どのようなデメリットがあるのでしょうか?
自発的な学習ではない
宿題は、学校から出されたものに子どもが家庭で取り組みます。
ですから、子どもの主体的な学習とは言えません。
これは「宿題=嫌なもの」というイメージの原因にもなります。
親にとっても普段が大きい
宿題は、子どもだけでなく親の負担にもなっていることが多いようです。
- なかなか取り組んでくれない
- いちいち質問されて困る
- 音読や計算カードのチェックが大変
- 丸つけも親の仕事
最近では働くお母さんも増えたこともあり、宿題を見るのが夜遅くになってしまうということもあるようです。
効果が出にくい宿題とは

さて、宿題についてメリットとデメリットを見てきました。
では、「特にこんな宿題には気をつけた方がいい!」という、効果が出にくい宿題とはどんなものか確認してみましょう。
量が多すぎる
量が多すぎると子どものやる気を削いでしまう原因になります。
また、多すぎて時間がかかると子どもの集中力も持続しません。
宿題は、学年×10分(1年生なら10分、2年生なら20分)を目安に終わる分量にとどめるのが理想です。
難易度が高すぎる
宿題が難しすぎる場合も時間がかかりすぎてしまいます。
そもそも取り組もうと思えず、やる気の低下に繋がってしまいます。
宿題は復習としての役割を持ち、学校で学んだ内容を定着させることが目的です。
しかし、宿題の難易度が高すぎると、復習にもなりません。
小学校で宿題はいらない?宿題のメリットは?まとめ

宿題には、メリットとデメリットそれぞれの側面があります。
- 授業の内容を復習できる
- 学習の習慣が身につく
- 子どもの学習内容を親が知ることができる
といったメリットがある一方で、
- 自発的な学習ではない
- 親にとっても負担が大きい
といったデメリットがあります。
宿題の効果を最大限生かすためには、
- 子どもに適した量
- 子どもに適した難易度
を設定してあげることが大切です。
学習に対する理解度ややる気は子どもによってそれぞれです。
子どもたちが、楽しんで学習を進められるような宿題になるように、学校や家庭でサポートしてあげられると良いでしょう。